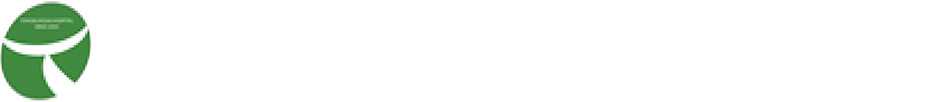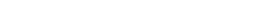臨床研究
当センターでは、宗像予防医療部長が責任医師となり、以下の臨床研究を進めております。
課題名:勤労者における体成分評価の意義と、食習慣および運動習慣の変化が体成分に与える影響に関するパネルデータ分析(令和7年1月~令和11年3月)
研究責任者:東京労災病院治療就労両立支援センター 加藤 宏一
研究の意義・目的
近年、人間ドックなどで体成分分析が普及しており、水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪などが測定されています。これらの体成分は、一般住民や高齢者を対象とした研究で、食習慣や運動習慣などの生活習慣、さらに脳血管疾患、心疾患、糖尿病、がんなどの様々な生活習慣病の発症と関連があることが示されています。しかし、働いている勤労者全般を対象とした研究はまだ不十分です。一般住民と勤労者では研究結果が異なる可能性があるため、勤労者の作業関連疾患の予防に体成分分析をより効果的に活用するには、勤労者に関するデータや知見が必要です。そこで、本研究では、独立行政法人労働者健康安全機構の予防医療データを以下の目的で分析します。
- a. 体成分測定値の参照値を開発します。
- b. 体成分と生活習慣病との関連を明らかにします。
- c. 生活習慣と体成分との関連を明らかにします。
研究の対象となる方
2015年4月から2024年3月までの期間に、独)労働者健康安全機構が運営する全国の労災病院に併設された治療就労両立支援センター及び治療就労両立支援部(以下「センター(部)」と呼ぶ。)の医師や専門スタッフから生活習慣病等の予防対策に関する指導を受けた方のうち、利用時の年齢が20~79歳であった方。来院された方だけでなく、センター(部)の医師や専門スタッフが事業場に訪問して指導を行った方も含みます。
研究の方法
(分析1)
体成分分析の結果を性別、年齢、身長別に平均値として算出し、参照データを作成します。ここで、体成分分析の結果とは以下の項目を指します:体水分量、細胞内水分量、細胞外水分量、細胞外水分率、タンパク質量、ミネラル量、体脂肪量、骨格筋量、BMI、体脂肪率、ウェスト・ヒップ比。
(分析2)
勤労者と非勤労者における体成分分析結果と、脳血管疾患、心疾患、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症との関連の有無およびその強さを、統計学的手法を用いて検証します。
(分析3)
勤労者と非勤労者における喫煙、飲酒、不規則な生活と体成分分析結果との関連の有無およびその強さを、統計学的手法を用いて検証します。
(分析4)
勤労者と非勤労者における食習慣と体成分分析結果との関連の有無およびその強さを、統計学的手法を用いて検証します。
(分析5)
勤労者と非勤労者における運動習慣と体成分分析結果との関連の有無およびその強さを、統計学的手法を用いて検証します。
分析に用いる情報
- 1. 健診データ ※健診等を実施された方のみ
- 2. 体成分分析データ ※体成分測定を実施された方のみ
- 3. 問診票(生活習慣病に係るアンケート)データ
- 4. 職業情報データ
- 5. 睡眠・食習慣・運動習慣アンケートデータ
なお、データには、氏名、生年月日、住所、保険証番号、診察券番号など、個人を直接識別できる情報は含まれていません。
研究組織
- 東京労災病院治療就労両立支援センター 加藤 宏一
- 東北労災病院治療就労両立支援センター 宗像 正徳
- 中部ろうさい病院治療就労両立支援センター 河村 孝彦
- 山陰労災病院 水田 栄之助
- 中国労災病院治療就労両立支援センター 豊田 章宏
- 労働者健康安全機構 木津喜 雅
課題名:過労死の要因となる脳心血管病の発症・再発に関する研究
(平成27年度〜29年度 厚生労働省 労災疾病臨床研究事業)
(平成27年度〜29年度 厚生労働省 労災疾病臨床研究事業)
主任研究者:神戸労災病院 井上信孝
申請書抜粋
過労死の主要な原因疾患である急性心筋梗塞や脳血管障害は、糖尿病、高血圧、脂質異常症等の危険因子によって惹起される動脈硬化を基盤とし、その発症には精神的ストレスが大きな役割を果たしている。高血圧、脂質異常症、糖尿病等の危険因子は、酸化ストレスを亢進させる。
本研究は、虚血性心疾患と脳血管障害に焦点をあて、発症・病態の進展過程をストレス応答の観点から包括的に検討し、過労死予防、脳心血管病の二次予防に関して新たな指針を確立することを目標とする。さらに、健常者を対象に、勤務状況が、心血管系生体ストレス応答に及ぼす影響を検討する。平成 27 年度では、生活習慣症例において、職業性ストレスと精神的ストレスとが深く関連することを明らかにしたが、平成 28 年度では、こうした知見をさらに発展させ、勤労者に対して、脳心血管病予防のためのきめ細かい指導ができるような指針の確立を目指す。そのために、本研究は、以下の検討項目からなる。
検討1:虚血性心疾患と脳血管障害の発症機転の検討
急性心筋梗塞、急性冠症候群、大動脈解離にて入院した勤労者、及びその既往のある勤労者を対象とし、発症時の職歴、勤務状況、生活歴、環境の変化、ライフイベントの有無等のアンケート調査を行う。必要に応じてインタビュー・面接による詳細な調査を行う。また同時に血圧、脂質値、血糖値、HbA1c 等を診療録から把握する。こうした検討により、急性心筋梗塞・大動脈解離の発症に関連する要因を明らかにしていく。
検討2:虚血性心疾患と脳血管障害の再発、病態進展のプロセスの検討
急性心筋梗塞、脳血管障害の既往のある症例に対して、発症時から現在までの病状の推移、再発の有無等、危険因子の経過を評価する。さらに現時点での精神的ストレス、職場ストレスの状況を定量的に評価する。さらに酸化ストレスマーカーLOX-Index の関連、抑うつにて変動する脳由来神経栄養因子等と関連を検討する。こうした検討により、脳心血管病の再発、病状の推移に関連する要因を明らかにしていく。
労災病院ー心血管病 ストレス研究
Rosai-Stress-Cardiovascular-Study: RSCS
Rosai-Stress-Cardiovascular-Study: RSCS
【対 象】
- 1)急性心筋梗塞、急性冠症候群、狭心症、大動脈解離にて入院した勤労者
- 2)急性心筋梗塞、急性冠症候群、狭心症の既往のある外来通院中の勤労者
- 3)人間ドックを受診した勤労者(コントロール)
【評価項目】
ストレスアンケート 精神的ストレス SDS/PSS 職業性ストレス JCQ職歴、勤務状況、生活歴、環境の変化、ライフイベントの有無等のアンケート調査を行う。
血圧、脂質値、血糖値、HbA1c 等を診療録から把握する。労働ストレスが過多であると思われる症例の関しては、インタビュー・面接による詳細な調査を行う
【検討・評価】
- ・Case-Control Study
- ・急性心筋梗塞、急性冠症候群、大動脈解離に発症に関連する因子の解明
- ・心血管病再発、悪化に関連する因子の解明
【主な研究施設】
神戸労災病院 井上信孝 研究担当事務:福山和恵
東北労災病院 宗像正徳
関西労災病院 上松正朗
山陰労災病院 太田原顕
労働安全衛生総合研究所 吉川徹
労働安全衛生総合研究所 久保智英